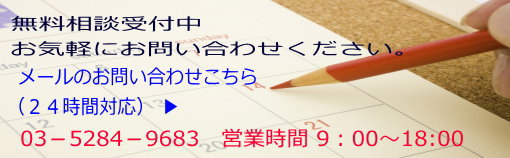IT業の個人事業主を応援する足立区北千住の山田一成税理士事務所(確定申告・創業)
お気軽にお問い合わせください。03-5284-9683 Mail : it@office-kyamada.com
トップページ → IT業の個人事業主を応援する税理士事務所

足立区北千住の山田一成税理士事務所(やまだ かずなり)
足立区千住仲町19-5 オーデーパナハイム4階( 北千住駅西口下車 徒歩5分)所属: 東京税理士会 足立支部(登録番号 117234) プロフィールはこちら
足立区北千住の山田一成税理士事務所のホームページはこちらです。
初回の相談は無料
IT業・ソフトウェア業の個人事業主として独立開業はしてみたものの、
個人事業主として「確定申告」をしなければならないのか不安です。
確定申告をする場合においても、相談する相手もいないし、何をどうすれば良いのかわかりません。
今回、初めて確定申告を行う予定の個人事業主の方、毎回、確定申告を行っているが、
再度、ご確認したい個人事業主の方は必見です。
ここでは、確定申告の基本中の基本についてご説明したいと思います。
確定申告は要点さえつかめば、意外と簡単にできるものです。
税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。

山田一成税理士事務所の代表は、ソフトウェア開発会社において、
プログラミング作成・システム詳細設計・システム総合テストなどの実務を経験し
約6年間、ソフトウェア開発業界に従事していた経験があります。
税理士業界は60歳以上の高齢者が50%超を占めているため、
ソフトウェア業に従事していた税理士は、ほぼ皆無に等しく貴重な存在だと思います。
ソフトウェア開発業の発展を会計・税務から全面的にサポートすることを使命と感じております。
平成28年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。
■ 平成28年分の確定申告の費用・料金・報酬
■ 税理士報酬の事例
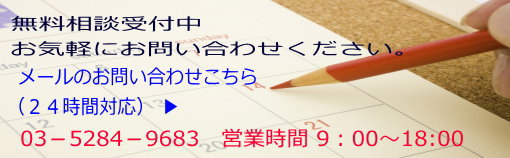
IT業の個人事業主を応援する税理士事務所(確定申告・創業)
IT業(個人事業主)の確定申告の概要についてはこちら
■平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度
■確定申告の概要(IT業)
■確定申告に関連する税金の種類
■IT業の個人事業主の青色申告の手続き方法は?
IT業(個人事業主)の事業所得の計算の概要についてはこちら
■IT業の個人事業主(事業所得)の所得の計算
■IT業の個人事業主(事業所得)の収入金額に算入するもの
■IT業の個人事業主(事業所得)の収入金額に該当しないもの
■IT業の個人事業主(事業所得)の必要経費に算入するもの
■IT業の個人事業主(事業所得)の必要経費に該当しないもの
平成27年10月1日からの適用開始
国内外のデジタルコンテンツの発信等のサービスに係る消費税の課税関係の見直し
IT業(個人事業主)の消費税・創業・節税等についてはこちら
■ソフトウェアは償却資産税の課税対象?
■消費税の簡易課税の事業区分(IT業・ソフトウェア業)
■小規模企業共済の加入の検討(IT業)
■税理士報酬の事例(開業3年以内のIT業の個人事業主)
■IT業の創業計画書の記入例(日本政策金融公庫より)
■平成28年分の確定申告の費用・料金・報酬
■アフィリエイトの確定申告・節税対策(山田一成税理士事務所)
■クラウドファンディングの確定申告(山田一成税理士事務所)
平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度
平成26年1月からは事業所得等を有する白色申告の方についても 記帳・帳簿等の保存する制度の対象
となります。
上記の条件に該当する個人事業主の方は、注意が必要となります。
※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
■記帳する内容について
①売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、
・取引の年月日
・売上先・仕入先その他の相手方の名称
・取引金額
・日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
②記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、
簡易な方法で記載してもよいことになっています。
■記帳等の保存について
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受取った請求書・領収書
などの書類を保存する必要があります。
①帳簿の保存期間
・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)→ 7年
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) → 5年
②書類の保存期間
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類 → 5年
・業務に関して作成し、又は、受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 → 5年
■書類の保存義務(収入金額)
収入金額を証明するために、契約書(控)・領収書(控)などの書類を保存。
※ 1取引当たりの金額が5万円以上で100万円以下の場合には、200円の収入印紙を貼付し
消印します。
「平成26年4月1日以降」の領収書の収入印紙の貼付は、3万円以上ではなく、5万円以上になります
ので注意が必要です。
書類の保存義務期間は、原則7年(重要)です。
■書類の保存義務(必要経費)
必要経費を証明するために、契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
①領収書を受領する場合:日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは必ず記載してもらうこと。
②レシートを受領する場合:レシートも領収書と同様に証拠資料となるため、必ずもらうこと。
③領収書を受領することができない場合:出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に添付します。
(冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機でのジュース購入など。)
書類の保存義務期間は、原則7年(重要)です。
確定申告の概要(IT業)
■所得税は、「事業所得」・「給与所得」・「不動産所得」など10種類の各種所得から構成されている。
主な所得の種類は、以下のとおりです。
①事業所得:個人事業主やフリーランスなどの営む事業から生じる所得
②給与所得:会社員・OL・アルバイトなどの給与から生じる所得
③不動産所得:土地建物などの不動産の貸付けから生じる所得
④譲渡所得:土地建物・株式などの売却した場合に生じる所得
⑤雑所得:原稿料・講演料やOL・主婦などの副業から生じる所得
※所得税の計算は、10種類の「各種所得」を合算して税額計算を行う。
■所得税の計算期間は、 毎年1月1日~12月31日
(1年間の各種所得の金額に基づいて所得税額を計算します。)
■所得税の申告納付期限は、 翌年2月16日~3月15日
■確定申告書の提出場所は、(原則)住所地の所轄の税務署
(国税庁のホームページにて確認することができます。)
■所得税の納付場所:金融機関(銀行・郵便局など)、住所地の所轄の税務署
確定申告に関連する税金の種類
■所得税(毎年3月15日までに納付。)
■個人住民税(所得税を基礎に、地方公共団体が税額計算を行う)
■国民健康保険(一部は、所得税を基礎に、地方公共団体が税額計算を行う)
■個人事業税(所得が一定額以上の場合には、地方公共団体が税額計算を行う)
■消費税(一定の要件に該当する場合には、原則、申告及び納付を行う)
※「所得税」及び「消費税」は、納税者が確定申告を行い、申告期限までに申告及び納付を行います。
IT業の個人事業主の青色申告の手続き方法は?
(Q)IT業を個人事業主として開始する場合の手続きはどうすればよいのか?
(A)
■IT業を個人事業主として開始する場合には、個人事業を開始した日から1ヵ月以内に、
「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の税務署に提出しなければならない。
■確定申告の申告方法には、
「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。
①税務署に「青色申告承認申請書」を提出していない場合には「白色申告」です。
②税務署に「青色申告承認申請書」を提出している場合には「青色申告」です。
■「青色申告承認申請書」の提出期限
①その年の1月15日以前に、新たに事業を開始した場合には、
その開始の日の属する年の3月15日まで。
②その年の1月16日以後に、新たに事業を開始した場合には、その開始の日から2ヵ月以内。
(例)H27.4.9にIT業として事業を開始する場合 → H27.6.8までに提出
③白色申告者が当年度から青色申告の承認を受けようとする場合には、
承認を受けようとする年の3月15日まで。
(例)「白色申告者」が平成27年から「青色申告者」となる場合 → H27.3.15までに提出
個人事業主(事業所得)の所得の計算
■個人事業主は、事業から生じた所得(事業所得=本業)について確定申告をする必要があります。
■事業所得の計算方法は、以下のとおりになります。
事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 -(青色申告特別控除額)
■所得税の計算方法は、以下のとおりになります。
① 課税所得金額 = 事業所得の金額 - 所得控除額
② 所得税の額 =(課税所得金額 × 税率)
③ 納付額 = 所得税の額 - 税額控除 - 源泉徴収税額
■用語の意味
① 総収入金額とは、収入金額の合計額です。
② 必要経費とは、個人事業の収入金額に対応する部分の費用です。
③ 青色申告特別控除額は、10万円と65万円のいずれかの金額です。
④ 所得控除額とは、個人的事情や家族構成を考慮して所得の一部を免除。
⑤ 税額とは、課税所得金額から「所得税額計算表」に照合して算定。
⑥ 税額控除とは、所得税の額のうち一部を免除します。
⑦ 源泉所得税額とは、所得税の額の前払い分です。
IT業の個人事業主(事業所得)の収入金額に算入するもの
■ IT業の総収入金額は、収入金額の合計額をいいます。
IT業の収入金額のうち、主なものは以下のとおりになります。
① 市場販売目的のソフトウェア収入
② 受注制作目的のソフトウェア収入(請負契約)
③ 受注制作目的のソフトウェア収入(準委任契約)
④ 受注制作目的のソフトウェア収入(派遣契約)
⑤ 受注制作目的のソフトウェア収入(SES契約)
⑥ 自社利用のソフトウェア収入(ASP等)
⑦ 自社利用のソフトウェア収入(コンテンツ配信)
⑧ 自社利用のソフトウェア収入(処理結果提供)
■ IT業の収入を売上高(収入金額)に計上するタイミングは、
IT業の収入金額が入金された日ではなく、IT業の収入が確定した日に計上します。
■ 例えば、IT業の収入の入金日が平成27年6月15日でも、
その入金された金額が、平成27年5月に確定したIT業の収入の場合には、
売上高の計上時期は、平成27年5月になりますので注意してください。
個人事業主(事業所得)の収入金額に該当しないもの
■普通預金の利子(「利子所得」に該当し、税引後の金額が入金されます。)■原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
■自動車などの固定資産の売却収入(基本的には「譲渡所得」に該当。)
■不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)
IT業の個人事業主(事業所得)の必要経費に算入するもの
IT業の個人事業主(事業所得)の必要経費は、
IT業の個人事業主(事業所得)の収入金額に対応する部分の費用をいいます。
IT業の個人事業主の必要経費のうち、主なものは以下のとおりになります。
① 取材費 ② コンテンツ商材費
③ コンテンツ制作代行費 ④ レンタルサーバー代
⑤ HP作成料・広告料 ⑥ IT業の関連本
⑦ セミナー・交流会参加費 ⑧ IT業の関連の協会の会費
⑨ 地代家賃(事業用部分) ⑩ チラシ・名刺作成・印刷費
⑪ 交通費 ⑫ 減価償却費
⑬ 消耗品・備品類(10万円未満) ⑭ 水道光熱費のうち事業用部分
⑮ 携帯電話などの通信料のうち事業用部分 など
個人事業主(事業所得)の必要経費に該当しないもの
① 生活費② 所得税・個人住民税
③ 国民健康保険・国民年金(「所得控除」に該当。)
④ 医療費・生命保険料・地震保険など(「所得控除」に該当。)
⑤ 住宅借入金等の利子
⑥ 携帯電話などの通信料のうち家事用部分 など
ソフトウェアは償却資産税の課税対象?
(Q)今年の6月にソフトウェアを300万円で購入したのですが、このソフトウェアは、償却資産税の課税対象となるのでしょうか。
(A)結論から申し上げますとソフトウェアは償却資産税の課税対象とはなりません。
償却資産税の対象とならない資産の中に、無形固定資産が含まれており、
ソフトウェアは無形固定資産に含まれるため償却資産の課税対象とならないと思われます。
パソコンと一緒にソフトウェアを購入する場合には、
見積書や請求書の明細は、パソコンの本体価額とソフトウェアの購入価額
を区分することが償却資産税の節税に繋がります。
国内外のデジタルコンテンツの発信等のサービスに係る消費税の課税関係の見直し
GoogleやAmazonなどの国外事業者からのコンテンツの発信等のサービスについては、これまでは、消費税は、課税されていませんでした。
平成27年10月1日からは、国外事業者からのコンテンツの発信等のサービスについても消費税が課税されます。
消費税法では、「電気通信利用役務の提供」と呼んでいます。
電気通信利用役務の提供に該当する取引は対価を得て行われる下記の取引になります。
■インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア
(ゲームなどの様々なアプリケーションを含む。)の配信
■顧客に、クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
■顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
■インターネット等を通じた広告の配信・掲載
■インターネット上のショピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
■インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
■インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト
(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
■インターネットを介して行う英会話教室
電気通信利用役務の提供に該当する取引の具体例としては、
①Kindleやkoboなどの電子書籍
②itunesなどの音楽配信
③DropboxやGoogleDriveなどのクラウドストレージ
④GoogleAdwordsなどのネット広告
国内外のデジタルコンテンツの発信等のサービスに係る消費税の課税関係の見直しの制度の仕組みや留意点
などについて、国税庁が公表している「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」に関する
リーフレット、Q&Aを参照してください。
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」(国税庁HP)
消費税の簡易課税の事業区分(IT業・ソフトウェア業)
IT業・ソフトウェア業の売上高がその年において1,000万円を超える場合には、その年の翌々年のIT業・ソフトウェア業の売上高に対して消費税を納付しなければなりません。
消費税の納付の方法としては「原則課税」と「簡易課税」の2種類の方法があります。
■原則課税
(売上でお預かりした消費税) ー (経費として支払った消費税)
■簡易課税
(課税売上高に対する消費税) ー (課税売上高に事業区分のみなし仕入率を乗じて計算した消費税)
※1.消費税を納付する前々年の売上高が5,000万円超の場合には適用できません。
2.適用を受けようとする年の前年までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
3.当該届出書を提出した場合には、簡易課税は継続して2年間は強制適用です。
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定しています。
日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・「小分類」の3区分に分類します。
ソフトウェア業は、 ① 大分類 G-情報通信業
② 中分類 情報サービス業
③ 小分類 ソフトウェア業
簡易課税の事業区分は、第五種事業に該当することになります。
■ ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業も第五種事業に該当します。
■ 情報処理・提供サービス業・インターネット付随サービス業も第五種事業に該当します。
簡易課税の事業区分の詳しい内容につきましては、以下のHPを参照してください。
消費税の簡易課税の事業区分(国税庁HP)
(具体例)
平成26年からIT・ソフトウェア事業を開始したものと仮定。
(従業員は0名でブログやシステム管理などは、全部外注に委託している状況です。)
1.IT業・ソフトウェア業の売上高の推移
① 平成26年の売上高: 950万円
② 平成27年の売上高:1,200万円
③ 平成28年の売上高:1,500万円
④ 平成29年の売上高:1,800万円
2.消費税の課税の有無の判断
① 平成26年(第1期)及び平成27年(第2期)は免税事業者となります。
② 平成28年は平成26年の売上高が1,000万円以下のため、免税事業者となります。
③ 平成29年は平成27年の売上高が1,000万円を超えるため、課税事業者となります。
3.原則課税を選択した場合
① 平成29年の売上高に対する消費税額:1,440,000円
② 平成29年の費用に対する消費税額(経費率40%と仮定):576,000円
③ 平成29年に納付する消費税額 ①-②=864,000円
4.簡易課税を選択した場合
① 課税売上高に対する消費税:1,800万円×消費税率8%=1,440,000円
② 課税売上高に事業区分のみなし仕入率を乗じて計算した消費税:
1,800万円×50%(第五種事業)×消費税率8%=720,000円
③ 平成29年に納付する消費税額 ①-②=720,000円
5.最終的な判断
簡易課税を選択した場合には、原則課税を選択したときよりも
864,000円-720,000円=144,000円、消費税の負担を軽減することができる。
小規模企業共済の加入の検討(IT業)
(Q)IT業を個人事業主としてを経営していますが、「小規模企業共済」に加入することができますか。(A)「小規模企業共済」とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合
など、第一線を退いたときに、それまで積み立てた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
■ IT業の個人事業主の経営者の加入要件
①IT業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または法人(会社など)の役員
②小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
■ IT業の個人事業主の経営者でも加入することができない場合
①サラリーマンなどの給与所得者が副業で飲食業を行っている場合
※主たる事業が会社員であり、小規模企業者に該当しないためです。
②直接営利を目的としない法人の役員の方。
③「中小企業退職金共済制度(中退共)」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、
「林業退職金共済制度」の被加入者の方。
■ 掛金の取扱い
掛金月額は、1,000円~70,000円の範囲内で自由に選択できます。
加入後も掛金月額を変更することができ、支払方法も「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。
■ 税法上の取扱い
小規模企業共済の掛金を支払った場合、その支払をした年分の個人の所得から
「小規模企業共済等掛金控除」として、全額を控除することができます。
■ 共済金の受取りの取扱い
共済金は、加入後6ヶ月以降における廃業や退職などの事由が生じた場合、
掛金の納付月数を基準として法令で定められた額を受取ることができます。
満65歳以上で15年以上掛金を納付した場合、事業を継続していても共済金を受取ることができます。
共済金の受取方法は、
「一括」、「分割」、「一括と分割の併用」を選択できます。
■ 共済金の税法上の取扱い
①「一括」の場合には、「退職所得」として取扱います。
②「分割」の場合には、「雑所得(公的年金等)」として取扱います。
■ 「小規模企業共済制度」の具体的な内容は、以下のHPを参照してください。
小規模企業共済制度のHP(中小機構)
税理士報酬の事例(開業3年以内のIT業の個人事業主)
■IT業を営む個人事業主Aのケース(開業1年目)① 年 商:1,000万円未満
② 従業員:1名
③ 訪問回数:4ヶ月に1回(当事務所にて打ち合わせ。)
④ 仕訳数:毎月30仕訳未満(当事務所にて仕訳データを入力。)
⑤ 源泉所得税の納付:半年に1回の源泉所得税の特例
⑥ 償却資産:1,000万円未満
| 内容 | 月額支払額(税抜) | 年間合計額(税抜) |
| 月額顧問料 | 10,000円 | 120,000円 |
| 決算報酬 | 0円 | 60,000円 |
| 記帳代行料 | 0円 | 0円 |
| 源泉税納付書 | 0円 | 0円 |
| 年末調整 | 0円 | 5,000円 |
| 法定調書 | 0円 | 5,000円 |
| 償却資産申告 | 0円 | 0円 |
| 合 計 額 | - | 190,000円 |
■税理士報酬の割引のポイントは以下のとおりになります。
①お客様との打ち合わせの期間が4ヶ月に1回であり、当事務所にて行うことを前提としている。
②開業から3年以内のため経営者を応援することが当事務所の使命と考えている。
③年商が1,000万円未満のため消費税を対応する必要がないことを考慮している。
④毎月の仕訳数が30仕訳未満であり、仕訳数が少ないことを考慮している。
⑤従業員数が1名である。
⑥償却資産の価額が1,000万円未満である。
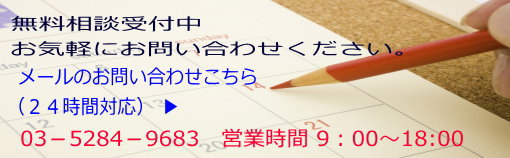
IT業の創業計画書の記入例(日本政策金融公庫より)
■創業の動機(創業されたのは、どのような目的、動機からですか。)
①勤務時代にソフトウェアの企画開発・制作・管理等に一貫して携わった経験を生かしたい
②元勤務先などからの支援もあり、事業の見通しが立ったため
■経営者の略歴等
1.経営者の略歴
①平成○年○月 ○工学学院卒
②平成○年○月 ㈱○システムズ(ソフトウェア開発業)7年勤務
③平成○年○月 ○データ㈱(ソフトウェア開発業)12年勤務
(プロジェクトリーダーを務める 当時の月給40万円)
④平成○年○月 退職(退職金200万円)
⑤現在 創業準備中
2.過去の事業経験 事業を経営していたことはない。
3.取得資格 ソフトウェア開発技術者資格(平成○年○月)
■取扱商品・サービス
1.取扱商品サービスの内容
①介護・医療施設用の顧客・財務管理システム開発(売上シェア80%)
300万円~1,000万円/件、開発期間3ヶ月~半年ほど
②医療関連機器のファームウェア開発(売上シェア20%)
○㈱からの業務請負、平成○年○月○日契約締結済
■取引先・取引関係等
1.販売先(回収の条件:末日/翌月末日回収)
①○データ㈱(○区○:元勤務先)(シェア70%/掛割合100%)
②医療法人A(○区○:元勤務先の販売先)(シェア30%/掛割合100%)
2.外注先(支払の条件:末日/翌月末日回収)
①○ソフト㈱(○区○:元勤務先の外注先)(シェア50%/掛割合100%)
②△データ㈱(○区○:元勤務先の外注先)(シェア50%/掛割合100%)
3.人件費の支払
末日/翌月25日支払い(ボーナスの支給月:6月/12月)
4.従業員
①従業員(うち家族):1名(0名)
②パート・アルバイト:0名
■お借入れの状況
○銀行○支店:住宅(お借入れの残高:2,554万円 年間返済額132万円)
■必要な資金(1,550万円)
1.設備資金(690万円)
①パソコン・サーバー等一式(○社見積のとおり)500万円
②事務機器(○社見積のとおり)70万円
③備品類(○社見積のとおり)20万円
④保証金 100万円
2.運転資金(860万円)
①外注費支払 270万円
②諸経費支払 590万円
※システム開発に、最短3ヶ月かかるため、つなぎ資金が必要
■調達の方法(1,550万円)
1.自己資金(550万円)
2.日本政策金融公庫(500万円)元金6万円×84回(年○.○%)
3.他の金融機関等からの借入(500万円)
○○銀行 元金6万円×84回(年○.○%)
■事業の見通し(月平均)
| 事業計画 | 創業当初 | 軌道に乗った後 (○年○月頃) |
| 売上高① | 300万円 | 390万円 |
| 売上原価② | 90万円 | 117万円 |
| 人件費 | 55万円 | 95万円 |
| 家賃 | 20万円 | 20万円 |
| 支払利息 | 3万円 | 3万円 |
| その他 | 75万円 | 95万円 |
| 合計額③ | 153万円 | 213万円 |
| 利益①-②-③ | 57万円 | 60万円 |
■創業当初
①売上高 300万円/件×1件/月=300万円(受注契約書あり)
②原価率(外注費)30%(勤務時の経験から)
③人件費 役員1名・従業員1名 30万円+25万円=55万円
家賃 20万円
支払利息(内訳)500万円×年○.○%÷12ヶ月=○万円
500万円×年○.○%÷12ヶ月=○万円 計3万円
その他光熱費、消耗品費等 75万円
※個人事業主の人件費は45万円(利益から報酬をもらいます。)
■軌道に乗った後
①売上高 創業当初の1.3倍(勤務時の経験から)
②原価率(外注費)30%(当初の原価率を採用)
③人件費 従業員1名増・当初の人件費増額分 計40万円増
その他諸経費 計20万円増
料金案内(山田一成税理士事務所のHPへ)
■ 法人顧問契約をご検討している方へ
■ 個人顧問契約をご検討している方へ
■ 年1回の決算申告(法人)をご検討している方へ
■ 年1回の確定申告(個人)をご検討している方へ
■ 税務相談・オプション
■ IT業の個人事業主の記帳代行・経理代行
■ 平成28年分の確定申告の費用・料金・報酬